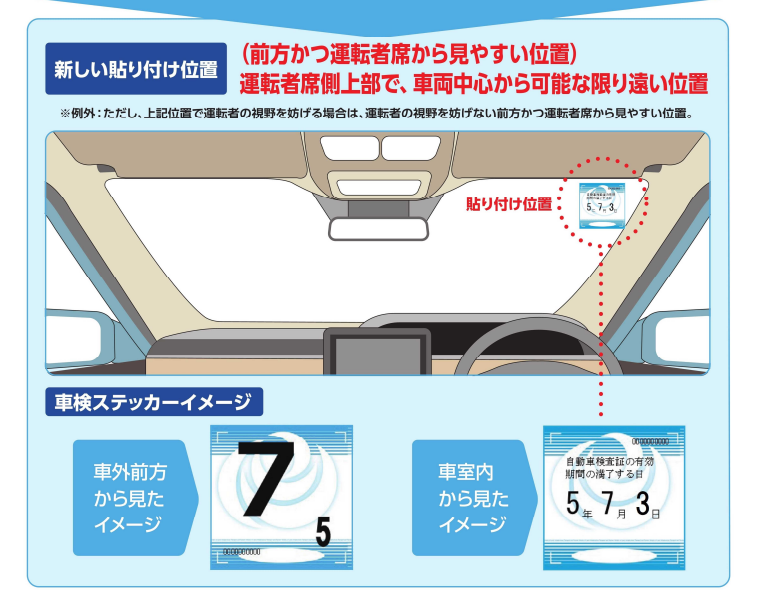車のエアコンから「ブーン」といった異音が聞こえると、不安を感じることがありますよね。
しかし、異音が発生したからといってすぐに大きな故障が起きるわけではありません。
早期に原因を特定し、適切な対処を行えば、修理費用を抑え、快適なカーライフを守ることができます。
本記事では、「ブーン」音が発生する原因から異音を解消するための具体的な対処法や予防方法まで解説!
異音を放置せず、早めの対応で車のエアコンを長持ちさせましょう。
車エアコンの「ブーン」音の原因とは?

車のエアコンは、複数の部品が協力して機能します。
そのため、異音が発生する原因はさまざまです。
具体的に「ブーン」音が出る理由について探っていきましょう。
1. エバポレーターの異物詰まり
エバポレーターは車内に冷たい風を送るエアコンの重要な部品で、冷媒が通過することで冷却され、その冷気が車内に送られます。
しかし、異物が詰まることがある部分です。
異物が詰まる原因は、フィルターの長期間未交換や車内の空気汚れ。
埃やゴミがフィルターを通過し、エバポレーターに詰まることがあります。
特に湿度が高いと、カビが発生しやすくなってしまうのです。
これらの異物が詰まると、風の流れが妨げられ、冷気が均等に供給されず、「ブーン」という音が発生することがあります。
2. エアコンフィルターの目詰まり
エアコンフィルターは、車内に流れ込む空気を清浄に保つ役割を担っています。
空気中のホコリやゴミを取り除き、車内の空気をきれいに保つために重要です。
しかし、フィルターが目詰まりすると、エアコンの冷却機能に影響を与え、風量が低下します。
目詰まりしたフィルターは空気の流れを悪化させ、エバポレーターやブロアファンに異物を送り込むことも。
その結果、「ブーン」という音が発生します。
フィルターが詰まることで、冷却効果が低下し、車内の空気の質も悪化してしまうのです。
3. ブロアファンモーターの故障
ブロアファンモーターの故障は、摩耗や異物の混入が主な原因。
モーター内部のベアリングが摩耗すると異音が発生しやすくなります。
また、道路からの埃やゴミがモーターに侵入すると、ファンの回転が妨げられ、「ブーン」という音が発生することも。
これが続くと、モーターの性能が低下し、最終的には動かなくなってしまうこともあります。
そのほかにもこんな異音が聞こえたら注意!

車のエアコンからは、「ブーン」音以外にもさまざまな異音が発生することがあります。
異音が発生した際には、その原因を早期に特定し、適切に対処することが重要です。
ここでは、エアコンからよく聞こえる異音とその原因について解説します。
1. 「カラカラ」「キュルキュル」という音
これらの音が聞こえる場合、ブロアファンモーターの故障や異物の混入が考えられます。
モーター内部の摩耗や、道路からの埃やゴミがファンに侵入することが原因。
風の流れが悪くなるだけでなく、モーターの性能低下にもつながるため、早期の対応が必要です。
2. 「ジー」「ギギギ」という音
「ジー」や「ギギギ」という音は、エアコンコンプレッサーの故障やベアリングの劣化が原因で発生することがあります。
この異音は、冷却機能に支障をきたす恐れがあるため、コンプレッサーの点検や交換が必要です。
3. 「シュー」という音
「シュー」という音が聞こえる場合、エアコンガスの漏れが疑われます。
パイプの接続部分やコンプレッサーのパッキンが劣化し、ガスが漏れることでこの音が発生してしまうのです。
エアコンの冷却効率が低下し、最終的には冷房が効かなくなる可能性があるため、早めに修理を依頼することが重要でしょう。
4. 「カチカチ」という音
エアコンのコンプレッサー付近で「カチカチ」という音がする場合、マグネットクラッチの異常が考えられます。
アクセルと連動して音が変化するため、クラッチが故障している可能性があるのです。
これを放置すると、エアコンシステム 全体に影響を及ぼすことがあるため、専門業者に点検を依頼しましょう。
全体に影響を及ぼすことがあるため、専門業者に点検を依頼しましょう。
車エアコンから「ブーン」音などの異音がする場合の対処法

「ブーン」という音が発生した場合、そのまま放置するとさらに大きな故障に繋がる可能性があります。
早期に対処することが重要です。
1. エバポレーターの清掃
エバポレーターに詰まった異物を取り除くには、エアコンの分解清掃が必要です。
エバポレーターは車内に冷たい風を送る役割を果たしますが、時間の経過とともに埃やゴミが詰まることがあります。
これにより風の流れが悪くなり、冷却効率が低下。
自分で掃除を行う場合、掃除機で周りの埃を吸い取ったり、市販のエアコン洗浄スプレーを使用することができますが、エバポレーター内部の汚れやカビを取り除くには専門的な清掃が必要です。
特にカビが発生している場合は、プロの整備士による分解洗浄が効果的でしょう。
定期的な清掃を行うことで、エアコンの効率を保ち、異音の予防にも繋がります。
2. エアコンフィルターの交換
エアコンフィルターは定期的に交換する必要があるでしょう。
交換の目安は1年または10,000kmごとですが、喫煙者やペットを同乗させている場合、より頻繁に交換することをおすすめします。
自分でフィルター交換を行う場合、車種によって交換方法が異なるため、車のマニュアルを確認することが重要です。
一般的にはグローブボックスを取り外し、フィルターを取り出して新しいものと交換します。
整備工場に依頼する場合、フィルター交換は比較的簡単な作業で、料金もリーズナブルです。
事前にフィルターの状態をチェックしてもらい、交換が必要かどうか相談してみましょう。
定期点検の際に依頼することもできます。
3. エアコンガスの補充
エアコンガスが不足している場合、まずはガスの補充が必要です。
しかし、単に補充するだけでは解決しないこともあります。
ガス漏れが発生している可能性があるため、その場合は整備工場での点検と修理が重要でしょう。
ガス補充は専門の機器を使って行いますが、補充作業は比較的簡単です。
しかし、もしガス漏れが確認されれば、修理が必要となります。
補充費用は車種やガスの種類によって異なりますが、一般的には数千円で補充が可能です。
ガス漏れが発見された場合、その修理費用が追加でかかることに。
そのため、エアコンガスの補充は専門の整備工場に依頼することをおすすめします。
自己判断で補充を行うと、適切な処置がされない恐れがあるため、プロによる点検を依頼し、安心な状態を保つことが大切です。
異音の予防方法と定期的なメンテナンス

早期に異音を防ぐためには、日常的なメンテナンスが重要です。
定期的にエアコンシステムの点検を行うことで、大きな故障を予防できます。
1. 定期的なフィルター交換とエアコンチェック
エアコンフィルターの交換を怠ると、異音が発生するだけでなく、冷却効果が低下します。
定期的な交換を行うことで、エアコンの効率を保ち、異音の予防にも繋がるでしょう。
さらに、車のエアコンが正常に機能しているかを確認するためには、簡単な点検方法を実施することが重要です。
例えば、冷却機能が正常か、風量に異常がないかをチェックしましょう。
定期的なチェックを行うことで、異音を早期に発見し、早期対処が可能になります。
2. 車内を清掃して空気を清潔に保つ
車内の空気を清潔に保つことは、エアコンフィルターの目詰まりを防ぐために非常に重要です。
車内のホコリやゴミがエアコンフィルターに溜まると、フィルターが目詰まりを起こし、エアコンの効率が低下します。
定期的に車内を掃除し、空気の質を保つことで、エアコンの不具合や異音を防ぎ、快適な車内環境を維持することができるでしょう。
また、車内の空気が清潔であれば、フィルターが長持ちし、冷却効果が保たれます。
車内の空気清浄を意識して、エアコンの状態を最適に保ちましょう。
3. 定期的にプロによるメンテナンスを受ける
エアコンの専門的なメンテナンスは、エアコンの内部で発生しがちな汚れや異常を早期に発見し、異音や故障を防ぐために効果的です。
プロの整備士は、エアコンの各部品が正常に機能しているかを徹底的にチェックし、必要な修理や部品交換を行います。
また、専門的なメンテナンスでは、フィルターやエバポレーターの洗浄だけでなく、ガスの充填やシステム全体の最適化が行われることが多く、エアコンが常に高い効率で運転できる状態を保ちます。
定期的なメンテナンスを受けることで、エアコンの寿命を延ばし、快適な車内環境を維持することができるでしょう。
専門業者に依頼することによって、自己流では気づきにくい問題を事前に解決し、修理費を抑えることができます。
エアコンを長く使い続けるためには、定期的な専門的メンテナンスが欠かせません。
まとめ

車のエアコンから「ブーン」音が発生した場合、早期に原因を特定して適切な対処を行うことが重要。
異音の原因として考えられるのは、エバポレーターの異物詰まり、エアコンフィルターの目詰まり、ブロアファンモーターの故障です。
これらの原因を放置すると、エアコンの効率が低下し、さらなる故障につながる可能性があります。
異音を防ぐためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
定期的な点検とメンテナンスを実施することで、エアコンの寿命を延ばし、快適なカーライフを維持することができるでしょう。
異音が発生した場合は、早期に対応することで修理費用を抑え、車のエアコンを長持ちさせることができます。
適切な対処を行い、車内環境を快適に保ちましょう。
古城モータースでは、オートブレーキホールドを搭載したお車を多数展示しております。気になる方はぜひ一度ご来店ください!!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
車検のYOU太郎について、ご案内★
YOU太郎車検は最短45分で車検が終わります!実際にお客様とお車を見ていただく立ち合い車検で透明性の高い車検を実現!当社では整備内容に関わる必要な個所はその場でお客様に確認して頂いております。1台に付き2名以上のスタッフにて車検を実施致しますので、一般工場よりも早くて正確な車検を行っております。石川県内、富山県内でもトップクラスの低価格車検の料金は【検査費用】と【法定費用】に分かれております。【法定費用】は主に国に支払う税金部分にあたりますのでどの車検会社でも同じ金額を支払わなくてはいけません。そのため、車検総額は【検査費用】で変わります。YOU太郎車検では事務手続き費用・検査代行費用は0円!古城モータースでは軽自動車からレクサス、ミニバン、4WD車、ハイブリッド車まで全て検査費用19,800円(税込)の同一料金です。低価格・短時間車検ではありますが、しっかりとお車の整備をさせていただきます!石川県の白山市、金沢市、野々市市、能美市、小松市で車検をお考えの方は、ぜひお問合せ下さい♪
金沢駅から車で30分 松任駅から車で10分
・車検のYOU太郎 石川白山店 〒924-0032 石川県白山市村井町1587-1 TEL:0120-540-418
・車検の速太郎 高岡店 〒933-0816 富山県高岡市二塚425 TEL:0120-540-118
・車検の速太郎 富山店 〒930-0996 富山県富山市新庄本町3-2-18 TEL:0120-506-540
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★